
公益社団法人 日本マーケティング協会発行 『MARKETING HORIZON』2017年2号掲載
わかっちゃいるけど難しい
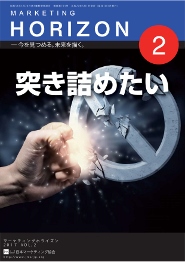
B to Cの事業を展開している方々にとっての永遠のテーマのひとつが「どうしたら我が社のこの商品(サービス)をひとりでも多くのお客さまに買っていただけるだろうか」というもの。
お客さまの気持ちを突き詰め、お客さまの気持ちに響く商品を開発し、そしてその商品の価値を届け、手に入れていただくこと。そこにおけるマーケティングの各プロセス上では詰めの甘さが許されるはずもなく、いくつもの調査ゲートをクリアすることが求められる。しかし、それらをクリアした上で満を持して上市しても、期待値に達するとは限らない厳しい世界。どの企業もあの手この手でお客さまの意識と行動、実態をリサーチし、戦略を講じるわけだが、結果としてなかなか突き詰められていないからこそ生まれたのが、今回の特集テーマである。言うは易し、行うは難し。実際はなかなか難しいよね。そんな担当者の嘆きがため息とともに聞こえてきそうだ。
買うことすらも面倒くさい
改めて述べるまでもなく、いまや「欲しい」と感じる気持ちと「買いたい」と思う気持ちの結び付きはどんどん弱く、そして複雑化している。そもそもミレニアル世代を筆頭にモノに対する「欲」は相対的に縮小しており、「面倒くさい」と感じる対象にすらなっている。店に行くのも面倒くさい、選ぶのも考えるのも面倒くさい、けれども失敗はしたくない、だからとりあえず一番売れているもの、一番メジャーなものを買っておく。一強多弱の傾向は強まる一方だ。
また、何かしらの「欲」が生まれたとしても、その実現手段はもはや「買う」だけではない。「借りる」「共有する」「つくる」など、買わなくても容易に満たされる環境が整ってきている。「買いたい」場合ですら、タッチするだけ、タップするだけ、ダッシュボタンを押すだけ、などにより、実は「お財布を開く」という言葉自体も既に体を成さない機会が急増している。お客さまに買っていただくまでの気持ちと行為のプロセスの変容はとにかく著しい。
そのうえ、競合の存在や意味までもが複雑化している。言うまでもなく競合商品は店頭で肩を並べる隣の商品だけではない。検索やランキングで上がってきた思いもよらないブランドや商品、時に想像すらしなかったカテゴリーが競合になる。また、過剰なほど「神様化したお客さま」に対応するための品質管理に汲々とせざるを得ない一方で、お客さま同士はフリマアプリ等を通じて化粧品など肌に付けるものですら使いかけの中古品を売買している。
さらに、お財布競合、時間競合まで考えていくと、いったい何をどこまでどう突き詰めれば十分と言えるのか、途方に暮れても致し方ない。
が、そうした環境はどの企業にとっても平等だ。残念ながら言い訳にはならない。だとしたら、まずはお客さまの「欲しい(手に入れたい、使いたい、試したい等々)」という気持ちをとことん突き詰め、理解し、共感した上で、それらを少しでも多く具体的なアクションに反映していくしかないのではないか。
まずは自社のプライドを突き詰める
よく言われるようにお客さまは理屈だけでは動かない。購買行動は不合理的で感情的な衝動に因ることも非常に多い。クオリティの高さや技術の先進性をいくら説かれても、それが自分事としてどのようにいいのかが直感的に刺さらなくては、例え100円であってもお金を払おうとは思わない。そのくせ、直感的に買うべき理由が生まれれば、理屈を超えて4ケタでも衝動買いできるものだ。技術開発担当者の努力の結晶である高い品質や新しい価値を、いかにお客さまの「よろこび」として伝え届けるか、まさにそれこそがマーケティングの腕の見せ所なのだ。
以下、お客さまに届ける際の突き詰め方のひとつのヒントを記したい。既知のことも多分にあるであろうが、これらを突き詰めたか否かは上市後に残酷なほど晒されてしまうものだ。ここに示すヒントを突き詰める価値は十分にあると確信している。
突き詰める対象は2つある。ひとつ目は自社のこと。実はお客さまのことを考える以前に明らかにしたい点だ。しかも、自社の強みが何であるか、ではなく「絶対に譲れないものが何なのか」を突き詰めたい。強みや弱みは自分で決めたり思い込んだりすることではなく、他者が決めることだ。しかし「これだけは譲れない」というその企業の、あるいはそのブランドのDNAもしくはプライドは、自ら育てていくものだ。この核がないといくら物性的には優れていても、自社のそのブランドのその商品でなければならない理由にはならない。何しろ機能だけなら同じようなものは他にいくらでもあるのだから。
安易にわかった気にならない
そして、突き詰める対象のふたつ目がお客さまのこと。顧客理解と表すとわかった気になりがちだが、これこそが最大の落とし穴である。
企画を担当する一個人としてはもちろん、組織やグループがわかった気になるリスク、わかったことにするリスクは非常に大きい。確かに、わかったことにすることで、誰も傷つかず、誰も悪者にならず、そして誰も責任を負うことはないだろう。また、突き詰める作法を間違えると攻撃的ムードになる可能性もあるため、社内や部署内において突き詰めることを無意識に回避している組織もある。だが、わかった気になってマーケティング・プロセスを進めた先に待っている当然の結果に対して、後からあれこれ理屈や解釈を付けても遅いのだ。ならば、はじめからとことんお客さまのことを突き詰めておこうではないか。
まずはターゲットとなるお客さまを特定すること。ペルソナ手法はそのひとつだが、大切なことは関係者の誰もが同じイメージと言葉でお客さまを語れるようにすることだ。たとえば「ワーキングマザー」「共働き世帯」といっても、夫婦共にフルタイムワーカーの場合と、妻が週3日のアルバイト就業の場合とでは生活のありようすべてが異なる。あるいは同じ週3日でも、例えば公文の先生として働くのと、自宅サロネーゼ(自宅でお教室等を主宰する主婦)としてプチ起業で働くのと、近所の歯科医で受付事務として働くのとでは、やはり大きく違う。突き詰める段階ではどのような人であるのか、明確に描いて狙い撃ちしたい。なぜか。お財布を開く購買時点のシーンの輪郭や背景がぼやけてしまう、いや、ぼやけるどころかそもそもその程度では描くことができないからだ。購買の瞬間を鮮やかに描き、代金と交換するときの心情を理解したい。
リサーチ手法も考え方も、時代と共に新しいものが次々話題になるが、顧客を理解する必要がなくなりました、というものはひとつもない。すべて顧客を理解するため、理解の仕方を助けるためのものである。そして、理解とは、わかったつもりになることではない。
常套句を禁句にしてみる
ところで、突き詰め方には非常にシンプルな共通のコツがある。それは、もっともらしい言葉を使わないこと。これに尽きる。
例えば、次のような言葉を禁句にするだけでも突き詰め方が変わる。
快適、簡便、安心、安全、健康、満足、笑顔などの漢字二文字を禁止する。これらは総論一致・各論不一致になりやすいため、コンセプトのブレにつながりやすい。また思考停止に陥りやすく、異論は出にくくなるが、各人の頭の中で描かれる具体的内容や価値のありようが一致しにくくなるため、曖昧なまま進みがちで、結果として手戻りが増えやすい。広告コピーを考える場面ではないので、簡潔な表現に仕立てるのは最終段階までお預けにした方がいい。いや、最終段階ですらあまりキレイに丸めない方が真意が伝わりやすい。
とにかく具体的な言葉やビジュアルで表現し尽くしていくことだ。どのような人の、どのような「よろこび」に貢献できるのか。競合他社ではなく自社だからこそ提供できるものは何なのか。それらを具体的に、全方位的に洗い出していく。わかりやすく言うと一般名詞ではなく固有名詞で「(こういうことって)あるある」「(こういう人って)いるいる」をとにかくたくさん描き、集めていこう、というものだ。従って、できるだけ年齢や属性の異なる関係者が集まって、お互いの視点やアイデアの「似て非なる部分」に驚いたり質問し合ったりしながら行うと良い。特に大手企業で働いている人たちは明らかにエリート層なので、年収300万円未満世帯の購買実態・生活実態を肌感覚で共感・理解することが難しい場合が多い。そのような時こそ定性調査等で実際の人たちとより多く接し、上から目線ではなく同じ目線の高さでありのままを受け止め、対象者の中から「この人をよろこばせたい!しあわせにしてあげたい!」と思える人や発言を探し当てることだ。
なんだ、そんなことか、と思うかもしれない。が、騙されたと思って、一度試してみて欲しい。実際に研修等で常套句使用禁止を言い渡すと一時的に手が止まり、時に「じゃあどう言えばいいんですか!?」とやや逆ギレ気味な質問も出るのだが、ナビゲートを進めていくと手応えを得ていくようで、企画に対する自信も得て、実際に企画そのものの魅力がイキイキと描かれていくことが多い。
突き詰める、とは一度あらゆる可能性を拡げたところからはじまる行為である。背景にそれだけの広さと奥行きを持っているからこそ、商品に対する理解と自信に繋がる密度が生まれるのだ。そこまで突き詰めれば、その魅力がバイヤーの方々やお客さまに伝わらないわけがない。

 『男性の育休』 家族・企業・経済はこう変わる(小室淑恵/天野妙 著、PHP研究所)
『男性の育休』 家族・企業・経済はこう変わる(小室淑恵/天野妙 著、PHP研究所) 『マーケティングの仕事と年収の リアル』 山口義宏 著、ダイヤモンド社
『マーケティングの仕事と年収の リアル』 山口義宏 著、ダイヤモンド社 30cm斜め後ろ
30cm斜め後ろ 103年愛し愛され続ける 宝塚の自画自“尊”オーラ
103年愛し愛され続ける 宝塚の自画自“尊”オーラ 家庭内年中行事にみる、しあわせな人vs.不満だらけの人
家庭内年中行事にみる、しあわせな人vs.不満だらけの人 やっぱり「行間」がいい
やっぱり「行間」がいい
